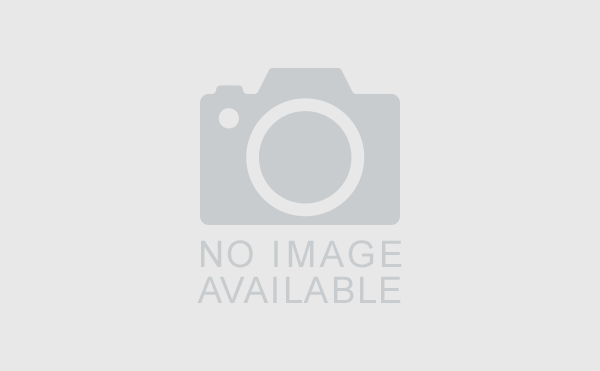「TOEICは役に立つのか」という不毛な問いをやめる日——「試験の点数」にすがる企業と受験者の心理を解剖する
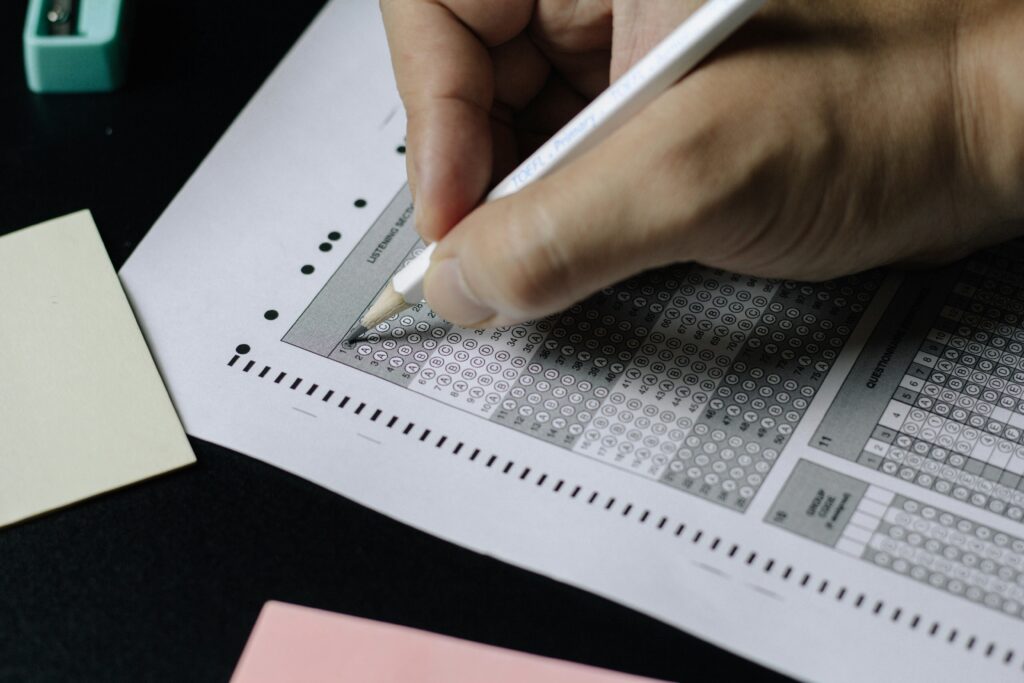
はじめに──「40年間繰り返される問い」に終止符を打つために
「TOEICって仕事に役立つんですか?」
この質問を、私は1988年に初めて聞きました。大学で就職を控えた先輩が「受けた方がいいらしい」と言い始めた頃です。以来、40年近く経った今もこの問いはネットのQ&Aや面接対策セミナー、企業の人事部でも変わらず繰り返されています。
そろそろ認めたほうがいいのではないでしょうか。
この問いは「自転車免許を取ったらツール・ド・フランスで勝てるのか」というくらい不毛だと。
それでもこの問いが消えないのは、企業も個人も「わかっているけれど、他に頼れるものがない」という現実を抱えているからです。今回はTOEICの歴史的背景、企業が求める理由、受ける側の動機、そして「試験の点数の先に何を問うべきか」を整理し、もう一段深い議論へと進めるための視座を提示します。
TOEICをめぐる背景と変遷
1980年代の日本でTOEICは「国際化の証明書」として導入されました。
1988年、私が初めてその名を聞いた頃、国内の受験者は数万人規模。企業派遣で受ける人がほとんどで、就職活動に書く学生はほとんどいませんでした。
しかし現在(2023年度実績)、年間受験者はおよそ240万人に達し、導入企業も1万4000社以上(IIBC公表データ)。「履歴書に書くもの」から「社内昇進要件」「新卒採用フィルター」にまで広がりました。
試験内容も変化しました。旧形式(2000年代初頭まで)は短文穴埋めやビジネス手紙の定型文などが多く、「ビジネス英語」というよりは「型にはめる英文法」が重視されました。現在はPart7の長文読解やPart3,4の実務的な会話・説明問題など、より「実用」に寄せた形式に進化しています。
受験する人の目的も多様化しました。
- 企業から「昇進条件」「新卒採用条件」として課される
- 社内の英語研修補助を得る
- 転職市場で武器にする
- 単純にモチベーション管理のため
一方、受験させる側の目的も多様です。
- 採用選考における英語力の足切り
- 社内の英語能力を可視化する
- 人事評価に反映するための基準作り
こうした「使う側」「受ける側」の多様化が、問題をさらにややこしくしているのです。
「TOEICは役に立つのか」という不毛な問いの正体
TOEICが仕事に役立つのか?
これを真顔で問うのは「水泳の検定で1級を取ったらクロールで荒海を救助できるのか?」と問うのと同じくらい皮肉な話です。
検定や資格はあくまで「一定の型」「再現性」を測るものです。しかし、実務で必要なのはその型をどの状況でどう応用するか、未知の問題を解く力です。
実はTOEICだけでなく、こうした「資格試験万能信仰」は日本社会の至るところにあります。
- 英検:面接まであるが、仕事の会話とは別物
- 簿記:仕訳はできても経営分析は別スキル
- 弁護士資格:取得しても交渉力や人間関係調整力は別
- 宅建、医師国家試験、IT系資格...枚挙にいとまがありません
それでも企業がTOEICを使い続け、受験者も受け続ける理由は単純です。
「他に簡単に測れるものがない」からです。
企業は分かっています。TOEIC900点でも会議で沈黙する社員はいる。逆に600点台でも実務で堂々と通訳レベルの対応をする人もいる。
でも採用の面接の段階で実務英語を検証する時間も人手もない。だから点数を足切りライン、目安、動機付けに使わざるを得ない。
企業も受験者も「割り切って使う」
ある上場メーカーの人事部長はこう言っていました。
「TOEICの点数が高いから即戦力とは思ってない。でも、英語をやってきたモチベーションや継続力を見る指標にはなる。」
別の総合商社の採用担当者は、
「スコア700未満の人でも素晴らしいバイリンガルがいるのは知ってる。でも一律に判断する基準がないと人を選べない。TOEICはそのためのフィルター。」
さらに、受ける側もしたたかです。
- 採用で有利
- 社内昇進要件をクリア
- 会社補助で教材を買う
- 給与が上がる
英語を実務で使って実績を出すのは時間も労力もかかります。しかし試験対策は体系化され、攻略法も満載です。
たとえば
- Part5文法問題の「型」で瞬殺
- リスニングで先読みをマスター
- スラッシュリーディングで解答スピードを倍に
これは「英語力」そのものというより「試験力」に近いスキルです。
では、どうすれば「役に立つ」かを見極められるのか
結局、「TOEICは役立つか?」を問うのではなく、
「この人が自社で必要な英語の仕事を再現できるか?」を問うべきです。
そのためには以下のような質問をプラスして面接で確認することをお勧めします。
- 「英語を使った仕事でどんな課題を解決しましたか?」
- 「TOEIC学習で得た力をどんな実務で応用しましたか?」
- 「英語を使った最も大変だった経験は何でしたか?」
また、企業としてはTOEICスコア以外にも以下をデータベース化しておくことが重要です。
- 過去の社内成功・失敗事例
- 必要なコンピテンシー(交渉力、調整力、粘り強さなど)
- キャラクター、姿勢、人柄
- 経験(留学、海外勤務、実務英語の頻度)
こうした事例の蓄積と分析なしに、「点数だけ」で人材を見極めようとするから、同じ不毛な議論が40年も続くのです。
結論と提言
TOEICの点数は役立つか。
「役立つかどうかは、その人がそれをどう使うか次第」です。
資格や検定は地図やコンパスのようなもの。目的地に辿り着くには、地図を読める力、実際に歩き続ける体力、状況判断の柔軟さが欠かせません。
企業は、点数だけを鵜呑みにせず、その先のコンピテンシーを問う面接設計をする。
受験者も、試験対策を「免許取得」にとどめず、自分の実務にどうつなげるかを考える。
双方がこの意識を持つことが、日本の英語力を「試験偏重」から「実践力」へ進化させる第一歩です。